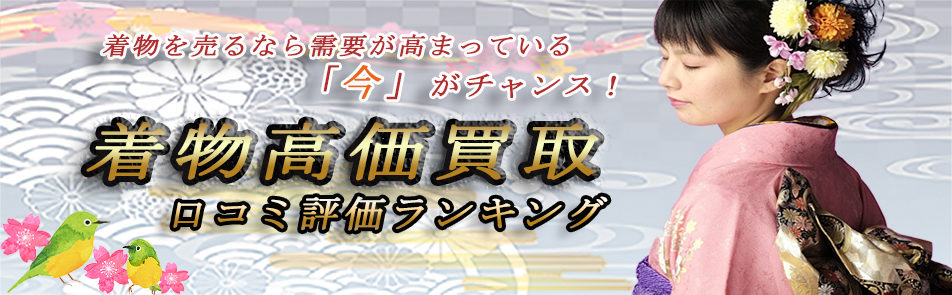
浴衣の種類について

夏になると男女を問わずお祭りに出かける浴衣姿を見ることが多くなります。毎年、夏場になって浴衣を着るのを楽しみにしている人も少なくないでしょう。
日本で着物と言えば、最も目にするのは浴衣かもしれません。浴衣は夏場に適した着物の1種ですが、その中で素材にはいくつもの種類があるのです。この記事では浴衣の素材や特徴についてご紹介しましょう。
夏の風物詩である浴衣
分類的には木綿の単の着物。浴衣という名前は、元々湯帷子(ゆかたびら)と呼ばれていたところからきています。一般的に浴衣は夏祭りなど、特定の行事にのみ着ていく着物と思われがちですが、じつは夏場の普段着として生まれました。もともとお風呂上がりに着る服として作られたのが始まりであり、そこから夏場の普段着としても着用されるようになった着物です。
浴衣生地の種類
浴衣のベースは木綿の単ですが、時代に合わせて様々な柄の浴衣が作られています。特に夏場のファッションとして人気を集めていることもあり、昔に比べ非常に多いバリエーションが取り揃えられるようになりました。
◆綿紅梅(めんこうばい)
薄い生地に対し、太めの糸を用いて縞状の模様や、格子柄を縫い付けることでデザインを整えた柄です。この際に描かれる格子柄が、凹凸になっているため、勾配からもじって紅梅と名付けられています。
◆綿絽(めんろ)
浴衣の綿生地に対して、横並びの穴が一定間隔で空いている浴衣生地です。このような状態を「絽目があいている」ともいうため、綿に絽があいているから「綿絽」と名付けられています。
◆綿縮(めんちぢみ)
先ほど目下糸を使って織り込まれた木綿の浴衣を指します。各種の糸を使って、表面にしぼみを作ることで仕上げられる綿織物の1種です。表面にしぼみができるため、外から見たときには独特の印象と風合いが楽しめます。
◆コーマ地
上質な木綿糸(コーマ糸)を使って作られる浴衣の総称です。コーマ地とも言われる浴衣生地を使って作られますが、一般的に目にする浴衣で広く使用されています。販売されている各種浴衣は、これらの生地の特性や柄を活用して、独自のデザインを織り込まれたものばかりです。いずれも浴衣には変わりありませんが、好みやコーディネートに合わせて、何着か浴衣を所有している人も少なくありません。
まとめ
一言に浴衣とは言え、日本文化である着物の1種です。量販店で大量生産されているものもあれば、職人が一つ一つ作成している浴衣もあります。それぞれの浴衣には、独自の魅力が秘められているため、夏祭りなどに行かない人でも、夏場の普段着として浴衣を着用してみてはいかがでしょうか。